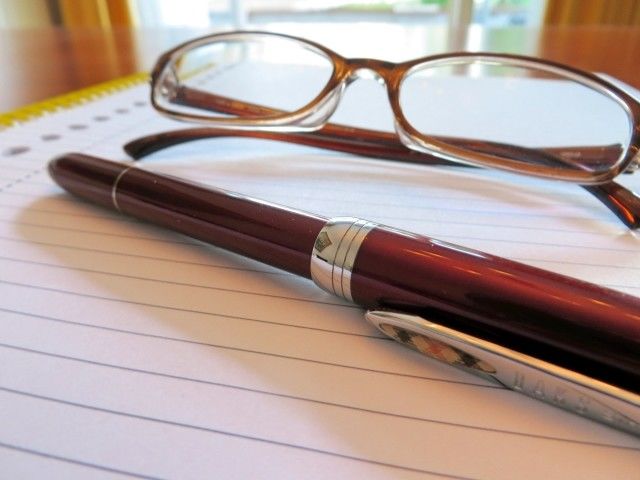
看護学校を目指す受験生には、「小論文」で悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
なぜ看護学校には小論文が出題されるのか。
小論文の書き方はどうしたらいいか。
看護学校ならではの小論文について。
少しでも受験生の力になれるように、まとめてみました。
(関連記事)この記事を読んでいる方にはこちらもおすすめです!
※看護実習レポートの書き方、上手なレポートとダメなレポート何が違うの?
※看護師の退職金ってどのくらいなの?辞めるタイミングが大事!
Contents
看護学校の入試には小論文がつきもの
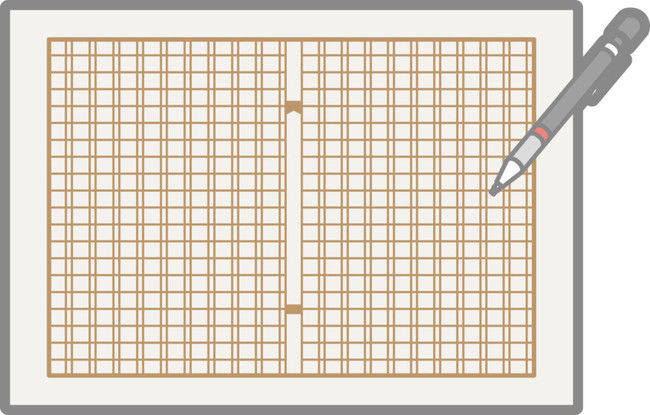
看護学校の入試には小論文がつきものといって良いくらい、多く出題されます。
看護学校だけでなく、医療系の学校全般にこの傾向があります。
それはなぜでしょうか。
小論文には、受験生の考え方、人格、これまでの学校生活、人間関係などが反映されてしまうものです。
そしてそれらは受験生の適性・資質をわかりやすくします。
医療を志すのは、すばらしいことです。
しかし、すばらしいのと同じくらい、厳しく、つらい道でもあります。
つまり、非常に本人の適性が重要な進路と言えます。
看護学校をはじめとした医療系の学校では、学校側が受験生の適性をしっかりと見定める必要があるため、入試問題に小論文が多く出題されるのではないでしょうか。
基本的な小論文のルールをチェック
まずは基本的な小論文のルールをチェックしておきましょう。
原稿用紙は正しく使えていますか?
パソコンやスマホで文章を作成することが多い昨今、段落が変わったら一マスあけるなどの原稿用紙のルールは意外に忘れられがちです。
改めて、原稿用紙のルールを確認しておきましょう。
また、いつ・どこで・誰が・なにを・なぜ・どのようにといった所謂「5W1H」が書けているか。
一人称は「私」であること。
である調か、ですます調か、語尾が統一されていること。
一文が長すぎではないか。
これら、読みやすい文章の基本も大切です。
そして、求められているのは小論文です。
単なる作文ではありません。
では、小論文と作文との違いとは、どこにあるのでしょう。
小論文は、自分の意見を結論とし、述べるものです。
自分がどう考えるか、意見をはっきりと書く必要があります。
そのため、「~思う」という言い回しは使いません。
一文の終わりは、言い切りの「である」、もしくは「~と考えます」とします。
新聞を読むと小論文対策になる?

新聞を読む習慣をつけましょう。
特に、医療関係のニュースについては必ずチェックしましょう。
単に読むだけでなく、普段からニュースについての考えをまとめておくようにしておきます。
また、天声人語や社説は、小論文に必要な資料の読み取りの練習にもなりますし、起承転結のある文章を構成する参考になります。
入試対策の定番・天声人語
上記した天声人語は、朝日新聞に掲載されているコラム。
時事問題や社会情勢について、あるいは身近な物事について書かれており、60年以上続いています。
そして天声人語といえば、中学校受験、高校受験、大学受験などで頻繁に引用される、入試問題の定番としても知られています。
つまり、天声人語をおさえておくことは、強力な入試対策になるというわけです。
天声人語を取り入れた授業を行っている予備校もあるくらいです。
天声人語は、603文字で書かれています。
▼で区切られた六つほどの段落に分かれており、起承転結のわかりやすい文章構成となっています。
入試では、天声人語が問題文として登場し、読んで答えるパターン、要約するパターンなどが出題傾向です。
また、天声人語そのものが出題されないとしても、日頃天声人語のような文章を読んでおくことは、小論文を書く際のお手本となり、役に立つものです。
小論文が頻繁に出題され、必須の対策である看護学校を受験するなら、天声人語を使った勉強は有効ではないでしょうか。
天声人語で読み取る力がつく
天声人語がなぜ小論文の対策によいとされているのかというと、まずは文章を読み取る力がつくからです。
起承転結がはっきりとした文章のパターンを読み慣れておくことで、小論文によく出題されるコラム、エッセイなどから意味を読みとりやすくなります。
そして、語彙力も豊富になります。
600文字前後という制約があり、万人にとって読みやすいことが求められる天声人語には、論文やコラムでよく使われる単語、言い回しが頻繁に登場します。
こういった語彙を持っていると、文章を読むのが格段にスムーズになるでしょう。
看護学校の小論文には、天声人語を始め、コラム、エッセイを読んで自分なりの考えを書くタイプの出題もあります。
こうしたタイプの小論文問題では、スピーディーに課題文を読む能力と、大切なポイントを読み取る能力が必要とされます。
天声人語を読み込むことで、これら読む力が鍛えられていくのです。
天声人語で書く力がつく
小論文には、文字数の制限があり、その中で自分の考え、意見をわかりやすく述べなくてはなりません。
その点、600文字前後で効率よく要点が詰め込まれた天声人語は、まさに小論文のお手本にうってつけです。
基本的な文章構成である起承転結がわかりやすいため、どのような流れで自分の考えを展開していけばよいかといったことも、参考になります。
わかりやすく、興味のもてる構成の文章の書き方が身につくでしょう。
文章を読んで自分の意見をまとめるタイプの出題は、読書感想文になりがちです。
自分の意見を述べる文章ならではの言い回しが多用されている天声人語を読み、参考にすることで、読書感想文ではない小論文が書けるようになるでしょう。
天声人語は、地球温暖化などの時事問題や、流行、風物を多く扱っています。
それら時事問題などについてわかりやすくまとめられているため、基本的な知識が身につきます。
そして、それら諸々に対する世論も、把握することができます。
天声人語を通じて多くの時事問題、流行、風物について日頃から関心を持つことで、あらゆる出題に対して自分なりの考えを展開することができるようになり、対応しやすくなることでしょう。
天声人語をどのように活用するか
まずは、天声人語を読むことです。
そして天声人語のテーマに対して、自分なりの考えをまとめるようにしてみましょう。
また、知らない単語・比喩・慣用句は調べる、使えそうな言い回しや表現をメモするなども有効です。
天声人語を書き写すのは、おなじみの小論文対策です。
専用の「天声人語書き写しノート」が販売されているほど、小論文対策としてはメジャーな学習方法です。
さらに、天声人語を読み要約をまとめるという学習方法もあります。
約600文字の天声人語を、さらに200文字に要約していくという方法です。
適切に情報を読みとり、まとめあげる能力が、ぐっと身につきます。
これまで出題された天声人語
「天声人語『マザー・テレサ死去 貧しい人々の救済にささげた生涯』」(滋賀医大/医/看護)
「天声人語『生活〈未来を生きる君へ 藤原帰一さんの伝言〉相手の立場 わかるためには』」(大分大/医/看護)
「天声人語を読み自分の考えを述べる」(秩父看護専門学校)
「天声人語を読み要約し自分の意見を述べる」(千葉県鶴舞看護専門学校/一般入試)
「天声人語の文章を読み自分の考えを述べる」(東京都立看護専門学校/社会人入試)
「天声人語を読んで戦争について書く」(華頂看護専門学校/推薦)
こうしてみると、大学の看護学部、看護専門学校の一般入試から社会人入試まで、ひろく天声人語が出題されていることがわかります。
要約文(200文字)と自分の意見(600文字)、二つの文章を書く出題もありました。
テーマが、看護・医療の天声人語だけとは限りません。
看護学校志望だからといってテーマを絞らず、さまざまな内容について書かれた天声人語を読んでおくと良いでしょう。
小論文の過去問対策
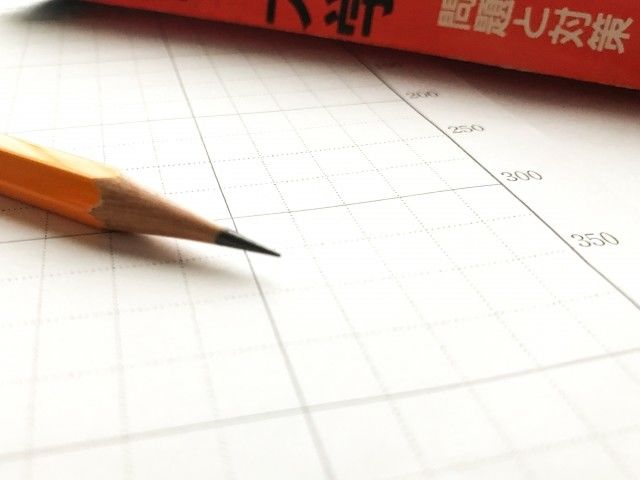
試験対策において、有効な手段のひとつが過去問対策です。
小論文も、過去に出題された内容を分析することで見えてくるものがあります。
過去に出題された小論文の出題形式、テーマの傾向、文字数、制限時間などを確認しましょう。
そして、同じ条件で小論文を書く練習をしておきましょう。
(関連記事)この記事を読んでいる方にはこちらもおすすめです!
※意外と知らない横書き原稿用紙ルール!記号や数字の書き方知ってる?
看護学校によくある出題形式
看護学校の小論文の出題形式は、大きく分けて二つのパターンがあります。
ひとつは、テーマ型。
「~について書きなさい」と、テーマを提示される出題形式です。
テーマから自分の考えを膨らませるので自由ではありますが、出題されたテーマについての知識が必要とされます。
日頃から多くのことに興味関心をもっているかも問われそうです。
もうひとつは、課題文型です
新聞の社説やエッセイ、コラムを読み、自分の考えをまとめるもの。
中にはDVDを視聴して答える、グラフを読みとり答えるもの、漫画から答えるもの、英語で書かれた文章を読むものもあります。
文章力だけでなく、あらゆる資料・情報の読解力が必要です。
テーマ型の傾向
また、過去の出題テーマについても、看護学校全体の出題傾向を確認すると、おおまかにいって以下のような傾向があります。
「人間関係・自分について」
「時事問題・社会問題」
「医療・健康について」
「目標について」
「経験・体験について」
テーマの傾向1 人間関係・自分について
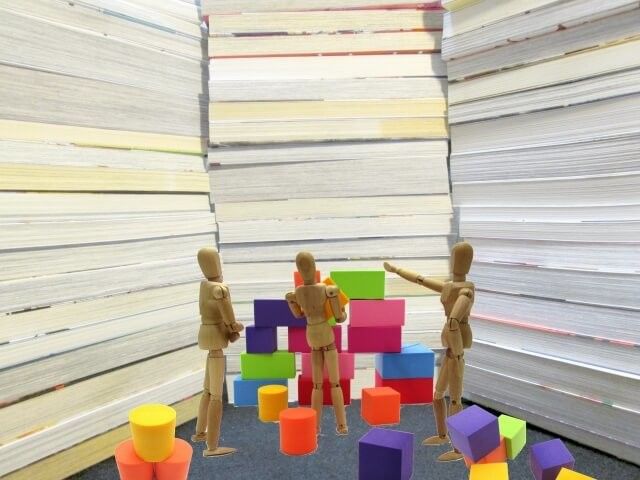
「出会ったなかで影響された人物について」(宮城県仙台市の看護学校)
「自分の判断での行動と、他人からの指示による行動を、体験を交えて書く」(神奈川県平塚市の看護学校)
「挨拶について」(静岡県浜松市の看護学校)
「桜の花は好きですか、嫌いですか」(愛知県名古屋市の看護学校)
「尊敬する人、苦手な人、意見が合わない人とどう接するか」(大阪府大阪市の看護学校)
一見すると、それじれのテーマはバラバラで、関連性は薄そうです。
しかし、よく見てみると、人との関わりや、受験生の人物像を連想させるテーマが多いことに気が付きます。
テーマの傾向2 時事問題・社会問題について
「臓器移植は人類に何をもたらすのか」(岩手県花巻市の看護学校)
「電子媒体の普及による活字離れについて思うこと」(愛知県新城市の看護学校)
「地球温暖化の原因と変化」(長崎県佐世保市の看護学校)
「高齢者社会に向けて私たちがこれからできること」(福岡県北九州市の看護学校)
「臓器移植の倫理について」(東京都荒川区の看護学校)
時事問題や社会問題も多く出題される傾向にあるようです。
特に、高齢化、介護、臓器移植など、命・健康・医療問題についてのテーマが多いようです。
日頃からニュースに関心を持つようにしておきましょう。
テーマの傾向3 医療・病気・健康について
「院内感染」(大阪府大阪市の看護学校)
「食中毒の猛威について」(鹿児島県鹿児島市の看護学校)
「ハンセン病患者とその家族について」(長崎県長崎市の看護学校)
「介護施設や病院等で最期をむかえる人がいることについて」(長崎県島原市の看護学校)
「『看る』ということ」(福岡県久留米市の看護学校)
看護学校という特性から、医療・病気・健康についてのテーマの出題はやはり多いようです。
医療への関心の高さ、考え方における適性などを見られているのかもしれません。
テーマの傾向4 目標について
「高校生活で学んだ事と入学後クラスで果たしたい役割について」(長崎県長崎市の看護学校)
「私の人生目標」(宮城県石巻市の看護学校)
「私が描く人生」(岐阜県大垣市の看護学校)
「10年後の私」(千葉県君津市の看護学校)
「あなたが理想とする看護者はどのような看護者か、あなたが理想とする看護者に近づくために、この学校で自分のどのような点を伸ばし、どのような点を直したいと思いますか」(埼玉県越谷市の看護学校)
入学後の目標について小論文にまとめる学校もあります。
志望動機にもつながる内容といえるでしょう。
人生について問われるものもあるので、自分についてみつめ、意志を持つようにしまでょう。
テーマ型の傾向5 経験・体験
「高校生活と友人」(秋田県秋田市の看護学校)
「介護ケアに関する文章を読んで要約し、自分の意見を体験談も盛り込んで述べる」(埼玉県熊谷市の看護学校)
「自分の判断での行動と、他人からの指示による行動を、体験を交えて書く」(神奈川県平塚市の看護学校)
「医療系大学を志望したあなたが高校時代努力したことについて」(愛知県豊明市の看護学校)
「『人の命』についてあなたの体験や見聞きしたことから思ったことや考えたこと」(大阪府大阪市の看護学校)
医療への日頃の関心度により、経験・体験やそれらに対する思い出も異なったものになってくるでしょう。
志望動機に関係しそうなテーマでもあります。
性格や、これまで取り組んできたことからの経験値も見られる内容かもしれません。
スポンサーリンク
課題型の傾向
「『高校生が覚醒剤を常用することについての〈自由〉』という新聞アンケートの結果についての考え(北海道札幌市の看護学校)
「新聞記事を読んで考えを述べよー覚醒剤・薬物使用」(東京都中野区の看護学校)
「芭蕉の句と解説を読んで」(千葉県千葉市の看護学校)
「ペエスケ」を読み自分なりにどのように考えたかテーマをあげて述べる(長野県飯田市の看護学校)
「天声人語を読んで戦争について書く」(滋賀県の看護学校)
多くは新聞記事、エッセイ、コラムなどの文章を読んで答えるものですが、詩・俳句の他、最近では4コマ漫画のようにユニークな課題もあります。
いろいろな例題を試しておくと、対応できる範囲が広がるでしょう。
社会人入試の傾向
「社会生活に関する文章を読み、自分の意見・体験を述べる」(東京都千代田区の看護学校)
「英文を読み、他人と協同して何かを成し遂げる上で必要なことについて、自分の意見を述べる」(神奈川県横須賀市の看護学校)
「これからの学生生活に社会人経験をどう活かすか」(神奈川県平塚市の看護学校)
「『職場におけるチームワーク』について自分の考えを述べよ」(兵庫県姫路市の看護学校)
「あなたにとっての壁とは何か。壁を乗り越えるためにどうしたらよいか、具体的に答えなさい」(兵庫県赤穂市の看護学校)
「どんな医療人になりたいか」(鳥取県鳥取市の看護学校)
社会へ出てから、改めて医療を目指す厳しさを乗り越える意志の強さや明確な目標が求められるような内容が目に付きます。
また、社会人ならではの経験を問うものもあります。
このように、社会人入試の小論文では、より志望動機や自己アピール的要素の強いテーマが多く出題されているようです。
(関連記事)この記事を読んでいる方にはこちらもおすすめです!
※小論文はどう書けばいい?作文との違いや構造、書く時の注意点は?
※どうしても書けない〜、そんな大学生のあなたに捧ぐレポートの書き方
字数と制限時間

小論文には決められた文字数と制限時間があります。
だいたい、小論文800文字を50分~90分間で書くことが多いようです。
決められた文字数内で、自分の考えをまとめて伝えなくてはなりません。
とは言っても、量が少なすぎるのも良くはありません。
総文字数の80%以上の文章量は必要とされます。
さらに、必要とされる文字数の小論文を、制限時間内に構成し、書かなくてはなりません。
普段から自分の書くペースをつかんでおいて、時間配分できるようにしておきましょう。
書いている途中でアイデアが浮かんでも、まずは最初の構成のままで結論まで書ききることを目標としたほうが安心です。
入試問題には必ず出題意図があります。
なぜ、その問題を出すのか。
その問題で何を評価したいのか。
そこには、必ず学校側の望むものがあるはずです。
小論文も同じです。
そのことを忘れず、がんばってください。
